|
建長寺 西来庵(僧堂)
2005.5.1.「建長寺僧堂春季講中祭」に、ご招待された時の
通常非公開で立ち入り出来ない建長寺 西来庵の撮影記録です。
(左の画像をクリックすると拡大します。)
 suusanmon suusanmon
嵩山門
西来庵(せいらいあん)に通ずる参道入り口の嵩山門(すうさんもん)。
ここから奥は修行道場になっており、非公開で立ち入り拝観は出来ない。
当日は、建長寺僧堂春季講中祭が行われたため、檀家招待者のみ入門できる特別の日である。

三門の右手、国宝梵鐘の脇にある。
当日は講中祭のため幔幕がかかっているが、通常は左の状況で門は閉められている。中央に「嵩山」、
左に「大覚禅師語録提唱」、
右に「本派専門道場」と掲げられている。
 seiraiangate seiraiangate
西来庵(僧堂)入り口の門。ここから入って左に食堂右に大徹堂(座禅堂)、奥に昭堂(国重文)、更にその奥に開山堂、開山堂背後の山に蘭渓道隆の墓がある。
 かかっている幔幕の家紋は、建長寺を建立した北条時頼に由来する北条家の家紋である。 かかっている幔幕の家紋は、建長寺を建立した北条時頼に由来する北条家の家紋である。
通常は左の状況で、立ち入り禁止になっている。
 gatehyouji gatehyouji
西来庵(せいらいあん)入り口の門に掲げてある額
 hondo hondo
門を入って左側にある食堂(本堂)。
春ぼたんがちょうど真っ盛りで建長寺全体に見事の花を咲かせていた。
 hondogenkan hondogenkan
食堂(本堂)入り口玄関。
右手に本堂大広間がある。
 hondosaidan hondosaidan
本堂内中央の祭壇。
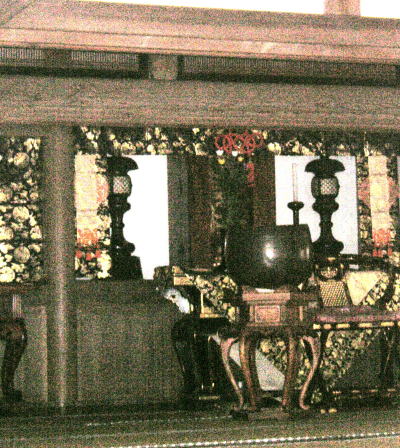
判別しにくいが、その場で見る雰囲気は極めて荘厳である。
 hondobutuga hondobutuga
本堂祭壇右手にある仏画。
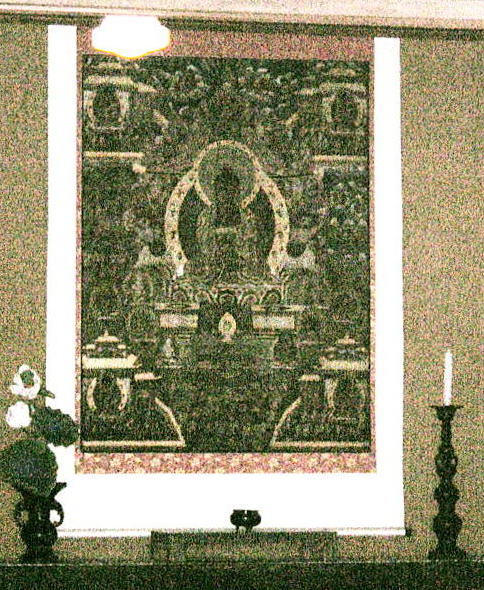
暗くて判別しにくい。
由来内容など不明。
 daitetudo daitetudo
大徹堂と掲げられている修行道場の坐禅堂。
 daitetudoiriguti daitetudoiriguti
大徹堂入り口左に吊り下げられている木板と木槌。相当磨り減っているが、時刻や座禅開始終了などの合図に打っているのかな。
 shousoumonju shousoumonju
聖僧文殊 大徹堂の主。
大徹堂(坐禅堂)入り口の仏像。
僧形の文殊菩薩像で、雲水は親しみを込めて「聖僧さま」というとか。
 daitetudonaibu daitetudonaibu
大徹堂内部。坐禅による修行の場所で、明り取りの窓からの光と、周りの静けさとあわせて、幽玄さを感じる雰囲気である。
 shoudo shoudo
昭堂。
開山大覚禅師(蘭渓道隆)が眠る塔所
正面に祭壇があり、中は太い柱で囲まれた暗いガランとした空間だが、修行の厳かさを感じる言葉にいえない雰囲気である。
この昭堂(しょうどう)は、国重文で1458年建造とされているが実際は江戸初期のもので、近世禅宗様建築の特徴を示している。
 shoudosaidan shoudosaidan
昭堂の中央奥にある祭壇。
開山大覚禅師(蘭渓道隆)をまつる。
 shukusha shukusha
西来庵入って左側にある建物。
笠や脚半がおいてあるので、修行僧のいわゆる宿舎かな?
 tokugeturo tokugeturo
大庫裏奥の得月楼における建長寺精進料理ふるまいの雰囲気。
これからいただく寸前。モデルの5名は誰でしょう?

こんなに広い得月楼大広間。
当日ここが満席になりました!
 shojin shojin
得月楼で供ぜられた精進料理。年に2回の講中祭の特別料理とかで、お酒二本(大本山建長寺 巨福)つき。
自然の恵みを味付けした素晴らしい味と香りの絶品である。
勿論お酒も最高!
TOPページに戻る
|